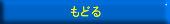|
| 広場より先はおそらく手押し軌道となり、なおも奥地を目指している。 | |
| 途中、左岸へ渡る橋が架かっている。片方はボロボロの吊り橋だ。渡ったところには建物が二つある。神社の付随施設だろう。 | |
| なおも奥へ。本によれば、この付近は木造の桟橋になっていたようだ。 | |
| 対岸に建物が見える。軌道はここよりもう少し奥でUターンし、あちらの岸の斜面を登っていくはずだ。 | |
| しばらく行くと、大きな橋が架かっている所へ着く。 | |
| A ここはかどや淵と呼ばれるところで、軌道はこの橋で左岸へ渡り、来た方へ戻りながら斜面を登っていくはずだ。橋は後年造り直されたものと思われ、そのためか半分までしか架かっていない。橋脚は軌道時代からのものと思われ、水の抵抗を減らすために上流側を尖らせるといった工夫が見られる。 | |
| 橋の上からは興味深い地形を見ることができる。岩壁が狭まり、門のようになっているのが見えるが、その先から轟々と水の落ちる音が聞こえる。その先にあるのが幻の滝と言われている大滝だ。ここからでは岩の陰になっていて見通すことはできない。見るためには、きつい岩場を乗り越えていくか、川を泳いで門をくぐるしかないのだ。神社の御神体はこの滝だそうだ。大滝神社はこの左手の斜面の上の方にある。神社の裏手に行けば、滝を上から見下ろすこともできる。 | |
| 橋の上から下流を見る。右岸が今まで歩いてきた道だ。青く塗られた橋が見える。一方左岸には平場が見られない。軌道が続いていたのは間違いないため、ここも桟橋になっていて、撤去されて残っていないのだろうと思う。 | |
| そう判断できる材料に、岩にある不自然な窪みがある。橋脚を差し込んでいた窪みだろうと思う。自然に出来たにしては出来過ぎだろう。・・・・そうであろう? さて、本で紹介されているのはここまでである。此処から先は情報が全くない、未知の世界である。 ここでお知らせである。この先7キロほどは並行する車道がないため、踏破するには一度で通り抜けなければならない。地形は大変険しく、攻略はかなり困難を伴う。此処から先への進入はお勧めしない。自分自身、踏破できたのは奇跡的だと感じているし、二度目はゴメンだと思っている。また、探索当時はGPSロガーなど、自分の現在地を知らせるものを所有していなかった。ここまでは並行する車道があったため、自分の現在地がいくらかわかったが、この先はそれすらないため、掲載している地図は100%勘で作ったものである。 | |
| さて、左岸にわたってしばらく歩いたが、一向に平場が現れなかった。先ほど対岸から見た神社の建物の横まで来たが、その間、軌道跡らしき痕跡は見つけられなかった。桟橋がここまでずっと繋がっていたのだろうか? | |
| 建物を通り過ぎ、吊り橋の袂まで帰ってきた。 | |
| すると、すぐそばでレールを見つけた。 | |
| 桟橋が続いていたと信じ、なおも進んでいくと、前方の高い所に平場の有りそうな雰囲気を感じ取った。 | |
| B 当たりだった。ついに軌道跡と再会した。 | |
| ところが数分歩いただけで、早くも橋のない谷にぶつかってしまった。 | |
| 急傾斜地を通っているため、上にも下にも迂回は困難であった。そこで岩や木を手がかりに水平に移動したが、その道中は穏やかでなく、しょっぱなからいきなり神経と体力を消耗してしまった。 | |
| 渡ってから気づいたが、起点側の足元には、崩れず見栄えの良い橋台が残っていた。 | |
| こういう事(橋のない谷)はこれっきりゴメンだと思っていたが、この時点ではまだ、安居の恐ろしさに気付いていなかった。 | |
| 僅か二分後。一本橋。これは架けたものだろうか? 倒木が偶然こういう形で残ったのではないだろうか? 渡れないか試してみたが、途中で折れて悲しい結果に終わるのが見えたので、ここも谷底を渡ることにした。 | |
| 起点側の橋台は角も崩れずしっかりと残っている。終点側は巨石の上に直接橋を載せていたようだ。 | |
| 終点側から起点側を見る。 | |
| C 二連続で谷を超えると、今までとはうって変わり、傾斜のゆるい杉林へと入った。。 | |
| 杉林を抜けると、道筋は斜面でぷっつり途絶えていた。この時は、きっと崩落で埋まってしまったのだろうと思い、しばらく道なき斜面をへつっていたが、一向に平場は現れずだんだん傾斜はきつくなり、うっかりすれば安居川に転落しかねない状態になった。そこでもしやと思い、最初の斜面をまっすぐ登ってみた。 | |
| すると、上方の窪みからひんやりした空気が流れ出し、頬をなでるのを感じた。 | |
| これってあれですかね? | |
| あれですね? | |
| D うわっほい! 地図にないトンネルを見つけたぞ。事前情報のないトンネルを発見し、にわかにテンションが上った。名前がわからないので、勝手に大滝隧道と呼ぶことにした。 | |
| 洞内には枕木を除いた跡が残っている。 | |
| 入り口は埋没しかけており、次に大雨か地震でも来れば埋没してしまうかもしれない。いつまでも入り口にとどまるのは気持ちが悪かった。 | |
| トンネルを出ると、急な左カーブになっていた。 | |
| 終点側の坑口。こちらは保存状況が良い。坑口前がヤブ化していてこれ以上バックできない。さて、トンネルだけ見に行きたいと思った方に朗報だ。C地点の杉林は他と比べると比較的傾斜が緩く、安居川の河原までゆるやかな斜面が続いている。なので、途中で川を渡り、斜面をよじ登ってくれば、トンネルまでいくらか楽にたどり着ける。 | |
| トンネルを過ぎると、間もなく谷に出た。橋台は残っていなかった。 | |
| 谷を越えてしばらく行くと、路盤が深い窪みに続いているところがあった。 | |
| E 二本目のトンネルかと色めきだったが、そこはヘアピンカーブの深い掘割だった。 | |
| 麓から数えると七個目のヘアピンである。 | |
| 実は結構長い間、上の段と下の段が並走していたようだ。上から見ると、下の段の路盤が丸見え。 | |
| やがて、トンネルのすぐ後に渡った谷に帰ってきた。 | |
| 谷を渡るのに夢中で、終点側の橋台を撮り忘れたようだ。これは終点側から起点側を撮っている。 | |
| 同じく進行方向を撮る。 | |
| F そして間もなく、トンネルの上部へ差し掛かった。そこは小規模な切り通しとなっていた。 |